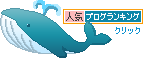作品データ
- 表題 本好きの下剋上
~司書になるためには手段を選んでいられません~ - 著者 香月美夜(かづきみや)
- ジャンル ファンタジー
- 出版社 TOブックス
- 初出 小説投稿サイト「小説家になろう」
- 連載期間 2013年9月~2017年3月(全5部677話完結)
- アニメ 第1部 2019年10月~12月(全14話)
第2部 2020年4月~6月(全12話) - コミック 第1部・第2部 鈴華 著
第3部 波野涼 著
あらすじ
この作品は,「小説家になろう」で連載された異世界転生もので,書籍化され,アニメ化され,コミカライズされ,ラノベガイドブック『このライトノベルがすごい!』の単行本・ノベルズ部門で2018年と2019年に1位を獲得している。
故に「ラノベ」と呼ばれる作品群に含まれると思われるが,壮大な世界観や練り込まれた舞台設定はとても「ライト」と言えるものではなく,ハリー・ポッターシリーズにも匹敵するほどのしっかりとしたファンタジー小説であると思う。
長い長い物語だが,表題が全てを語っている。
本狂いと言っても過言ではないほど本が大好きな女性が,司書になる夢を叶える直前に死亡。兵士の娘マインという5歳の病弱な少女として異世界に転生する。
しかし,マインが転生した家には本の1冊どころか,文字が見当たらない。
識字率がとても低く,紙も印刷技術も存在しない世界だったのだ!
その世界の本は羊皮紙に手書きで作る大変高価なもので,下町の労働者階級であるマインの家族には無縁なもの。両親は本と言われても「意味わからない」って感じだし,まともに字を読むこともできない。生活レベルは11世紀とか12世紀くらいだろうか。
トイレもシャンプーもないクオリティの低い生活であっても,本さえあれば耐えられる! そう思ったのに,本はないし,両親はひどく教養がない。マインは絶望し,怒り,不屈の精神で本に囲まれて暮らす生活を目指し始める。
本がないなら作ればいいじゃない。司書になってやる!
現代日本で読書をしまくって得た知識を生かし,マインは文字通り下剋上を繰り広げる。
紙の製法を確立し,職人を囲って活版印刷機を作り,本を出版し,人々の教養を高め,それらの過程で自らも平民から貴族へ,領主の養女へ,やがては女神の化身と言われるまでに地位を上げる。
そして最後には「本に囲まれた生活」を実現させるのだ。
第一部から第五部までの構成は下記の通り。
第一部は単行本3巻に渡るが,プロローグみたいなものだ。物語が進むにつれ,世界観が明らかになり,領地から国へと舞台は広がっていく。
第二部が全4巻,第三部が全5巻。第四部が全9巻。電子書籍(Kindle)では各々合本版が出ているので,そちらを読むと便利だ。第五部は書籍化途中だが,続きが気になったらWebで読める。
本好きの下剋上 ~司書になるためには手段を選んでいられません~
https://ncode.syosetu.com/n4830bu/
第一部「兵士の娘」(全3巻)
第二部「神殿の巫女見習い」(全4巻)
第三部「領主の養女」(全5巻)
第四部「貴族院の自称図書委員」(全9巻)
第五部「女神の化身」(?)
何しろ冊数が多いので,電子書籍の合本版がお勧め。
また父の仕事場を訪れた時,父の部下で文字が読めて計算が出来るオットーという男性と知り合い,文字を習う機会を得る。商人になる夢を抱いていたルッツに,以前は商人だったオットーを紹介して欲しいと頼まれたマインは気軽に紹介するが,そこにオットーの義理の兄,ギルベルタ商会の主人ベンノが現れる。そしてマインはベンノという後ろ盾を得て,紙作りを始める。
紙作りや髪飾りなどの商品を売るようになり,マインとルッツは商業ギルドへ登録。ギルド長の孫娘フリーダと知り合って,マインの熱が「身食い」という魔力によるものだということがわかる。身食いは貴族が持つ高価な魔術具を使わないと,遠くない未来に命を落とすことになるということだった。しかし,マインは貴族へ自分を売り込むことより,残された時間を家族と過ごすことを選ぶ。
そんな中で,マインとルッツは揃って洗礼式を迎え,儀式のために神殿を訪れる。
どうせ死ぬのだと思っていたマインだったが,神殿で巫女見習いになることが決まり,生きながらえることが可能となる。
神殿に入ったマインが考えることは図書館で読書をすることばかり。静かな読書時間を確保したいがために何故か孤児院長をすることになる。だが,孤児院をマイン工房にすることで,紙の製造を進めていく。
また前世で食べていた美味しい食事をもう一度実現したいという想いから,ルッツやベンノを巻き込んでイタリアンレストランの準備を始め,活版印刷のために職人を探したりと奔走しまくる。
自分のやりたいことしか見えていなくて,この世界では誰も知らない「グーテンベルク」の名前を出し勝手に称号にしてはしゃぐマインがウザくてたまらないが物語は面白い。
領主のジルヴェスターが登場し,物語は大きく動く。
貴族関係の登場人物がいきなり増える。母となったエルヴィーラに兄となったエックハルト,ランプレヒト,コルネリウス,養父母のアウブ・エーレンフェスト(ジルヴェスター)と第一夫人フロレンツィア,義理の兄ヴィルフリート,義理の妹シャルロット,新たな護衛騎士のブリギッテとアンゲリカ,新たな側仕えリヒャルダとオティーリエ。
ハッセの町に新しい孤児院を作ったり,ブリギッテの故郷であるイルクナーで紙作りなど事業を広げていく傍ら,貴族の派閥争いの陰謀に巻き込まれていく。
2年間眠っていたローゼマインは,ただでさえ小さかったのに2年間を失い規格外の小ささ。一人だけ小さくて目立つのに,貴族院でも図書館まっしぐらの考え無しの行動で悪目立ち。麗乃時代(前世)はこうだったからと単純に気安く言動する稚拙さが不思議すぎるが,ヴィルフリートとコルネリウス,そしてリヒャルダのローゼマイン管理の優秀さは一つの見どころ。
貴族院に入って,貴族の印であるシュラーブを得て,通信手段のオルドナンツを扱えるようになる。またディッターという貴族の騎士達が好む独特のスポーツが登場。
貴族院で注目を浴びるローゼマインをエーレンフェストに留めておく策として,ローゼマインとヴィルフリートは婚約することになる。
隣の大領地アーレンスバッハや領地内の旧ヴェローニカ派貴族との軋轢の中で,ランプレヒト兄様に花嫁がやってくる。
ターニスベファレンの件で聖典に注目が集まり,物語が更に動き始める。関連して,中央の聖典至上主義者と王族の問題など,視点がエーレンフェストから国全体へと広がっていく。
ローゼマインの貴族院での2年目が終わり,頼もしくローゼマインを守っていたコルネリウス兄様とハルトムートが卒業。王命が下ったフェルディナンドは,エーレンフェストを去って行く。
ネタバレ上等!言いたい放題
以下,ネタバレ無視で書き殴った好き勝手な感想。
本編を最後まで読み終えた方か,ネタバレを気にしない方のみご覧下さい。
主人公たるマインが兎にも角にもマジウザい!
「小説家になろう」冒頭の作者コメントで,作者自らが注意を促している。
曰く,
最初の主人公の性格が最悪です。ある程度成長するまで、気分悪くなる恐れがあります。
正直言って本当に主人公の性格は最悪だ。私に言わせれば,ある程度成長しても別に性格は改善されない。
マインは自分のことを「自重を忘れた女」と称しており,本人にもそういう自覚はあるようで,実に快いまでに自己中の極みを貫く。私は最後まで読み進んでもその性格を好きになれなかったし共感もできなかった。最後までマインのことは嫌いだった。
そもそも,元の世界では成人し大学を卒業し司書として就職まで決まっていた大人の記憶を持っているマインなのに,何故ここまでバカなのだろう?というのが最初の疑問。司書になれるほどしっかり勉強した人が,家の中の様子を見て,本が存在しないか,こんな貧乏な家には無縁な高嶺の花であることくらい容易に想像できないのだろうか。
前世の記憶を持っていても,5歳の少女の肉体に住んでいるため,身体が持つ幼い思考に引きずられているのだろうかと考察することもできる。だが,そうであるなら,本を作るために頭脳から引き出される知識は生半可ではない。いや,生半可どころの騒ぎではなく,専門書がそのまま頭に詰まっていても無理なレベルだ。あまりにもアンバランスだと思う。
物語を楽しむために,これらの矛盾は「俺TUEEEな転生チート」だと目をつぶることにしたのだが,引っかかりは消えなかった。
前世への異常な執着がマインのウザさに拍車を掛ける。
活版印刷技術の発明者とされるヨハネス・グーテンベルクは,この世界では確かに偉人だ。だが,この世界でだって11世紀や12世紀の人々に「グーテンベルクだよ!」と言ったところで理解されない。それなのに,マインは異世界の印刷技術以前の人々に向かって「グーテンベルク!」なのだ。意味不明に決まっていることが分からないのだろうか。大卒の図書館司書に分からない筈はない。
相手が分からないに決まっていることを知りながら,わざと意味不明な単語を使っているのか? 興奮のあまりそういった分別を失うほど人間性が未発達なのか?
グーテンベルクに限らず,このように前世の単語を当然のように持ち出して会話相手に突きつける事例はいくらでもある。極めつけが最後に領地の名前を決めるときだっただろうか。アレキサンドリアかベネツィア? 別の世界の実在の街の名を領民全体に押しつけるとは! いやはや私だったら心底止めて欲しい。
異常と言えば,マインの家族への執着も迷惑なレベルだ。
最初は本のために幾らでも利用し犠牲にする感じだった家族だが,前世の母親への申し訳ない気持ちを思いだした途端に最重要な存在となる。生まれた途端に引き離され会うこともなかった弟までを溺愛する。家族は領地の外へまでもマインについて行くが,詳しく書かれている街のギルドや組合の仕組みを考えると無理無謀な行為にしか見えない。マインに触発されて子供の頃から頑張った姉のトゥーリだけなら,マインの行く所へついて行って仕事をしようとするのもまだわかるのだが。
義理の妹シャルロッテに対してお姉様ぶりたい要求の激しさにも辟易だ。バカなの?
魔力や座学など能力だけ高く生意気で自己中な養女のマインが,そこまで尊敬と憧憬の念を持って領主一家の子供達に受け入れられ大切にされることが,とても不自然に思えた。ヴィルフリートもシャルロッテもメルヒオールも,嫉妬心など邪な心は一切無い澄み切った心を持つ人格者なのだろう。そうとしか思えない。
ほんと,この自己中で暴走だらけで自重を捨て去ったトラブルメーカーのマインが,義理の家族や側近達に非常に大切にされ愛され尊敬されていることが,最後まで不思議かつ納得できなかった。
ただ,マインの活動は領地や国家に大きな利益ももたらすので,利益を考えれば合点がいく気もする。
マインの魔力が王族などものともしないほど強大で,しかも全属性であるとかチートすぎるわけだが,一応マインが全属性であることや魔力が強くなったことは,この世界の仕組みに基づいて理屈で説明されている。
マインの自己中で破綻した性格は,大変不快なものではあるが,このように某かの大きな事をやり遂げ世界を変えてしまうような人には,こういった周囲の人のことなどお構いなしに突っ走るような異常さが必要なのだろう。周囲の人々に気を遣い,やりたいことを我慢するような心優しい人がマインのような業績を残すのは,難しいかもしれない。
ローゼマイン(マイン)にはイライラさせられっぱなしだったが,偏った分野では非常に賢いし機知に富んでいて面白い。
第四部『貴族院の自称図書委員 Ⅲ』で,マインが周囲の人物を家具に例えてフェルディナンドに語る場面があったが,興味深かった。
下町の面々は隠し部屋と寝台。
貴族院の自称図書委員 Ⅲ
お父様と養父様は、他者の進入を防ぎ守り外に出さないための扉。
エルヴィーラとリヒャルダは暖炉。明るく暖かく必要だけど近づきすぎると火傷する。
護衛騎士たちは大切な物を守ってくれる本棚。
ダームウェルは鍵のかかる書箱。
神殿の側仕えは執務机。公私の仕事をし本を読む。
ヴィルフリートは背もたれがない椅子。ひと息つけるけど寄りかかれない。
前ライゼガング伯爵は暖炉の上の棚の細かい細工の置物。
フェルディナンドは長椅子。本を読んで寛げる。でも完全に身体を預けて眠ってしまうとあちこち痛くなったり風邪を引いたりする。
マイン以上にチートなのはフェルディナンドの存在
第2部以降,マインと並んで主要人物となるフェルディナンド(神館長)。
もし彼がいなければ,マインは魔力の威圧で神殿長を殺し,その罪で処刑され,物語は第一部でさっさと終了してしまったことだろう。
そもそもフェルディナンドは,マインが神殿長を威圧したとき,何故止めたのだ? 放置してマインに神殿長を殺させれば,神殿長に苦しめられていたフェルディナンドとしては万々歳ではないか? これだけの魔力を持つマインは,今現在エーレンフェストに不足している魔力を得るための貴重な存在なので確保しておくべきと,瞬時に判断したのだろうか。しかも,フェルディナンド自身も威圧に巻き込まれて辛い状況の中だったにもかかわらず,少ない言葉でキチンとマインを正気に戻した。優秀すぎる。
マインが巫女見習いとして神殿に入った時,フェルディナンドは確か21歳。幾ら貴族院で全て最優秀の成績を収めた秀才で,領主の弟として貴族社会及びユルゲンシュミット(国)について詳しい知識を持っていたとしても,たかが21歳だ。大学3年生程度の年齢だ。
それなのに神殿業務をほとんど請け負い,領主の仕事を手伝い,騎士団の仕事を手伝い,その上マインの面倒まで細やかに見る。いや無理でしょう。できすぎ。
そう,「マインの面倒を見る」というのは並大抵の子供の監視ではないのだ。
マインは貴族や神殿の常識を持たないことは勿論,前世という異世界の常識で動き,次々と想像を絶した問題を起こし,敵を作りまくる。しかもマインはこれまた想像を絶した虚弱体質で,非常に気をつけていなければ簡単に熱を出して倒れる。
そんな非常識の化身のような彼女の尻拭いをし,教育を施すのだ。マインを教育し導くためにはマインを理解しなければならないわけだが,異世界の常識で動く彼女を理解するにはもの凄く柔軟な発想力が必要となる。だが,フェルディナンドは優秀な頭脳と論理的思考によって,この上なく上手にマインをコントロールするのだ。フェルディナンド自身の環境により必要だったにしても,製薬に精通し,虚弱なマインが活動できるように専属医師&専属薬剤師として健康管理まで完璧にこなす。チート過ぎる。
結局のところ,優秀で努力家でやることなすこと規格外で刺激的なマインをフェルディナンドはかなり初期から気に入っており,ローゼマイン(マイン)がしでかすあれこれに翻弄されつつ面白がってもいたのだろう。『第四部 貴族院の自称図書委員 Ⅲ』で,フェルディナンドが恩師であるヒルシュール先生に言った言葉が心に残った。
「飽きることがない、退屈とは縁遠い時間を過ごしております」
第四部 貴族院の自称図書委員 Ⅲ
ローゼマイン(マイン)がゲルラッハ子爵に毒薬を飲まされた時,倒れたローゼマインをボニファティウスから奪うように連れ帰りユレーヴェを施した時のフェルディナンドの鬼気迫る様子を見れば,この時既に,フェルディナンドにとってローゼマインはとても重要な存在になっていることがわかる。
物語後半になって徐々に,フェルディナンドがマインと双璧を成す規格外であることが分かっていくが,ユルゲンシュミットの建国神話に登場し歴代ツェントにグルトリスハイトを授けてきたエアヴェルミーンに対し,フェルディナンドは非常に無礼な態度で接し嫌われていることに驚いた。
マインに対してあんなにも貴族らしく上品に振る舞うよう教えていたのに,実のところ,彼自身,見事に表面上取り繕っていただけだったのだ。本質は回りくどい貴族の習慣とは正反対の合理主義者で,目標を達成するために必要とあらば最短で動く。
フェルディナンドは本質的にマインとそっくりな性格なのだった。
兎にも角にも,フェルディナンドが存在し,フェルディナンドがいるエーレンフェストにマインが生まれ二人が出会う。この二つがなければユルゲンシュミットは崩壊したであろうし,ユルゲンシュミットで印刷技術が発展する機会は何世紀も先になったことだろう。
アダルジーザの実であるフェルディナンドがエーレンフェストの領主一族として生きながらえていたことは奇跡であるし,異世界から転生した異常な性癖(本好き)を持つローゼマインの存在も奇跡。
二つの奇跡が絡み合って事が進んでいくのだから,マインの転生はそもそも英知の女神メスティオノーラが仕組んだこととしか思えない。
ローゼマインの側近たちが面白い
マインがローゼマインとなり貴族社会に取り込まれた時に,カルステッド一家や領主一家など登場人物がどっさり増えるが,その後ローゼマインが貴族院に進学すると,更に側近たちがどっと加わり,登場人物を覚えるのが大変になる。
しかし,この側近達が各々個性豊かで面白い。是非とも全員の性格や役割を把握しておくのがお勧めだ。
人気投票で常に上位に食い込むのはダームエルだったようで,確かにマインの最初の側近であるダームエルは,最後まで優秀な側近として活躍する。
しかし,他の側近達もなかなか楽しい。
ローゼマインの義兄で,ローゼマインが領主の養女となった時からずっと護衛をするコルネリウス。本当の兄のようにローゼマインと仲良しだし,過保護だ。しかしそもそもの血筋が良いせいか,優秀でどんどん頼りになる護衛騎士に成長していく。
コルネリウス兄様がいてくれると,私はいつも安心して読み進むことができた。アンゲリカの卒業後,コルネリウスの存在がどれほど心強かったか。コルネリウスの卒業後はどうしようかと思ったほどだ。その後はコルネリウスの婚約者レオノーレや旧ヴェローニカ派のマティアスなどがしっかり護衛してくれ安心だったが。
コルネリウスと同じくローゼマインが領主の養女となった時からの護衛騎士,アンゲリカ。
彼女はどう見ても良家のお嬢様にしか見えない美少女なのに頭を使うことが大嫌いで,騎士としては実に優秀。優秀な部分と残念な部分の落差が面白く,アンゲリカが出てくる度に楽しかった。脳筋の愛されキャラだ。
ローゼマインの義兄エックハルトとはお互い明後日の方向でお似合いで,アンゲリカとエックハルトの結婚生活というものがあるとしたら見てみたいものだと思う。
貴族院以降の側近で最重要人物はハルトムートだろう。
とにかくとても優秀でキモイ。ローゼマインを心底崇拝し,ローゼマインの素晴らしさを布教するために全力でその優秀さを使うのだ。頼もしいことこの上ないし,キモイことこの上ない。この若さでこんなにも優秀なのだから,将来はフェルディナンドに名を捧げて仕えるユストクスに負けない文官になること請け合いだ。
同じく異常なまでにローゼマインに心酔しているクラリッサとの婚約は,ローゼマインとフェルディナンドと同じくらい運命的な組み合わせと言えよう。クラリッサも実に危なっかしく優秀で頼もしかったものだ。
しかし基本的に自分勝手で非常識なローゼマインが,余りある欠点を全て受け入れた上で側近達に尊敬され大切にされることは,やはりとても解せない気がした。
側近はローゼマインの保護者たちによって厳しく選別され吟味されて選ばれているのだし,派閥争いなどを考えれば自分にとって都合が良い人物に肩入れして仕えることになるのはわかるが,能力は高いのに非常識な姫君など,裏では嫉みそねみ失笑の対象になりそうなものではないか? 彼女の身内のためなら何だってする性格は,優しさとはちょっと違う気がする。
ローゼマイン,あんなに性格が悪いのに尊敬されすぎだし愛されすぎだ。
マインの家族が不思議
マイン時代の下町の家族は,マインがどんな立場になろうとも見捨てることはなく見守り続ける。
マインと姉のトゥーリはめちゃくちゃ仲が良いし,父親は命を省みない子煩悩。母親は父より落ち着いているが,マインのために行動する覚悟は父親に負けない。
だが,仲の良い家族,愛に溢れた家族などという言葉一つで説明できないほど,いつまで経っても彼らはマインとの関係を重要視し続ける。彼ら自身の下町に根付いた生活があるはずなのに?
姉のトゥーリがマインやルッツに刺激を受けて上を目指して頑張るのは,まだわかる。だが,マインが街を出て移動するなら自分もと,幾ら仲が良かったとしても姉がいつまでも思い続けるだろうか。幾ら仲の良い姉妹であっても,成長し,成人し,幼い頃考えていたのとは異なる人生を歩んでいくのが普通だと思う。姉には姉の人生があり,恋人が出来たり,他にやりたいことができたりするだろう。
が,トゥーリの眼中にはそういったことは一切なく,将来マインが街を出て領地を出て行くならば,自分もマインについて行ってマインの役に立つ仕事をしようと考え,実行し,成人してもそれを貫く。
最後には両親もトゥーリも,マインには思い入れがないはずの弟のカミルまで,領地をまたいでマインのいる街へ引っ越して行く。トゥーリと母のエーファはローゼマイン専属職人という建前があるが,父親はその家族として仕事も辞めて引っ越すのだ。
街の職人達には各々ギルドがあって職人の世界にはしっかりしたルールがあるはずなのに,そういうのは良いのだろうか。
マインが貴族界へ引き取られ,元の家族とは一切関係ないと契約魔法を結んでから,トゥーリが成人するほどの長い年月が流れているのに。
ルッツやベンノなど商人達がローゼマインと共に移動して仕事をするのはわかるのだが,マインの家族に関しては何だかできすぎみたいな印象だった。
重ねて言おう,マインあんなに性格が悪いのに異常なまでに愛されすぎだ。
神話で彩られた世界観がよく作り込まれている
魔力が存在する世界が舞台となる物語は珍しくないが,ここまでしっかりと神話が作り込まれている作品は少ないのではないかと思う。
闇の神に光の女神,その子供達である五柱の神々,水の女神フリュートレーネ,火の神ライデンシャフト,風の女神シュツェーリア,土の女神ゲドゥルリーヒ,命の神エーヴィリーベ,そしてその神々の眷属。
神々の属性と貴族が持つ魔力は対になっており,自然現象までもが神々のご加護と魔力で説明される。
第一部では魔力は商人の契約魔法程度しか登場しないが,物語が進み世界観への理解が深まるにつれ,魔力と神々の関係が細やかに設定されていたことに気づき感動した。神話と世界の一体感がすごくて,この世界が実在していないのが不思議になったほどだった。
政治の仕組みは雑すぎる
ツェント(王)がいて国を治め,アウブ(領主)がいて領民を治め,ギーベがいて領地内の地域を管理する。年に一度の領主会議で国の重要事項は決定される。領主会議に出席するのは,王と領主と領主の第一夫人だ。領地内は貴族の冬の社交で何となく決まる?
王の命令には逆らえず,ほぼ絶対王政。領地内では領主に逆らえないが,大領地・中領地・小領地などの身分差で領主も他領地との関係は自由にならない。議会のような制度はなさそうで,王命と領主会議だけで国が動いているようだ。
マインの父親は兵士だが,軍隊の指揮系統がどのようになっているのかは謎。アウブの護衛は騎士団が行い,騎士団と軍?の関係もよくわからない。そもそも「兵士」は何に属し誰の指揮で動いているのか? 法律の仕組みも分からない。
まぁこのような設定がよく分からなくても物語には関係ないし,面白かったので特に問題は感じなかったのだが。