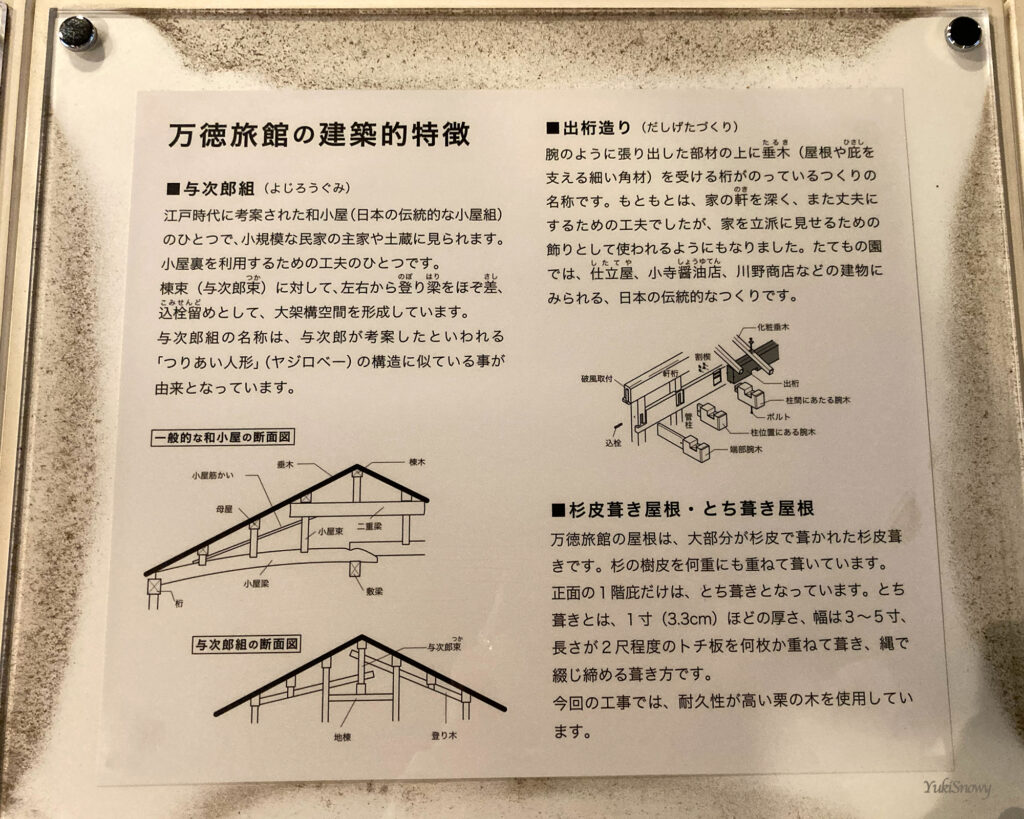江戸東京たてもの園の東ゾーン,下町中通り奥のT字路の東の端に建っている。
1879年(明治12)に文京区向丘1丁目に建てられた町屋で,内部は大正時代の仕立屋が再現されている。


こんな格子戸も下駄も,私が子供の頃だった昭和中期にはまだ普通に残っていた。懐かしい。


そして,この布を置いてある木製の裁台。
私の祖母(1903年生まれ)は和服を縫うことを生業としていたので,彼女の前にはいつもこの台があり,私には見慣れていた物だ火鉢や鉄瓶も懐かしい。


こんな湯呑みも,いつのまにやら旅館でしか見かけなくなった気がする。
まだ私の食器棚にも入っているけれど,使わないなぁ。
神棚の前に下がっているペンダントランプがお洒落だ。



2025年10月に見た風景である。